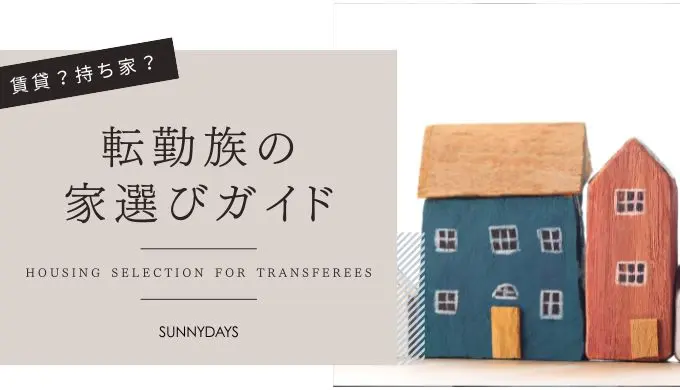
こんにちは、朝日千晴です。
転勤族の住まい選び、「賃貸のままが安心…?」それとも「家を買ったほうがいい…?」と悩んでいませんか?
私もまさに、その迷いの渦中にいました…。
そんな我が家ですが、昨年思い切って建売住宅を購入!現在は、夫は単身赴任先、私と子ども達は自宅で暮らす、2拠点生活をしています。
今回は、我が家が家を購入した理由と、その判断プロセスを、リアルな体験談とともにお伝えします。
賃貸か持ち家かで悩んでいる転勤族の方の参考になれば嬉しいです!

ライター/仕組みづくりアドバイザー。信託銀行を経て、フリーのWebライターとして活動を開始。現在は、書く仕事とあわせて「人にやさしい仕組みづくり」をテーマに、暮らしや組織が心地よく回るようサポートを行っています。

転勤族の住まいには、賃貸と持ち家それぞれにメリット・デメリットがあります。
そこで、まずは下の表で両者の特徴をわかりやすく比較してみました。
| 項目 | 賃貸 | 持ち家(単身赴任あり) |
|---|---|---|
| 住まいの柔軟性 | 転勤が決まればすぐ引越し可能 | 自由に移動するのは難しい |
| 初期費用・負担 | 敷金・礼金・仲介手数料程度 | 購入時の頭金・諸費用 ローン返済あり |
| 資産性 | 家賃は支出で資産にならない | ローン返済後は資産として残る |
| 費用 | 家賃のみ | ローン+光熱費+管理費+単身赴任費用で高め |
| 維持・管理の手間 | ほぼ不要(大家が対応) | 固定資産税、保険、修繕費 |
| 相続・手続き | 賃貸契約の名義変更程度で簡単 | 相続時の手続きや名義変更が 発生し、賃貸より手間 |
| 安心感・安定性 | 転勤先次第で変動 | 自宅がある安心感 老後も住める |
賃貸
- メリット:転勤や引越しに柔軟で、初期費用や管理の手間が少ない
- デメリット:家賃は資産にならず、老後の住まいの安定感が低い
持ち家
- メリット:資産として残り、老後や家族の安心感が得られる
- デメリット:ローンや維持費がかかり、相続や手続きが必要

賃貸と持ち家を比較すると、まず気になるのは「コスト」の違い。
では、実際に賃貸と購入でどれくらい費用に差が出るのか、具体的に見ていきましょう。
- 賃貸:家賃12万円/月(年144万円)、更新料は2年ごとに1か月分
- 持ち家:建売住宅 3,500万円(頭金なし、35年ローン/金利1.0%固定)、固定資産税10万円/年、修繕積立・リフォーム費:月1万円想定
| 項目 | 賃貸 | 持ち家 |
|---|---|---|
| 家賃・ローン | 144万円 | 123万円 |
| 更新料 | 6万円 | ー |
| 固定資産税 | ー | 10万円 |
| 修繕費 | 12万円 | |
| 合計 | 150万円 | 145万円 |
- 賃貸:5,250万円
- 持ち家:5,075万円
単純なコストだけで見ると、持ち家の方が35年間で約175万円お得です。
さらに、持ち家は住宅という資産が残る点もメリットといえるでしょう。
ただし、転勤族の場合、賃貸では家賃補助などが出ることも多く、実際の負担額には個人差がある点に注意が必要。
また、単身赴任の場合は二重で生活費もかかるため、ローンや維持費、光熱費など、すべての費用を含めて総合的に検討するのがおすすめです。
- 転勤族の場合、賃貸は家賃補助が出ることもあり、賃貸と持ち家どちらがお得かは人によって変わる!
- 持ち家は修繕費や固定資産税の負担がある
- 金利が上がると持ち家のコストは増える
- 住み替えの自由度は賃貸の方が高い
- ローンや生活費など、必要な費用を含めて総合的に検討するのがおすすめ

結婚当初から夫は転勤族で、私たちにとって数年に一度の転勤は当たり前。
夫婦ともに1人の時間を大切にするタイプなので、地元から離れて暮らすことにも抵抗はなく、むしろ「色々な所に住めて楽しい!」とポジティブに考えていました。正直、家を買うなんて考えたこともなかったんです。
そんな私たちが住宅購入を考え始めたのは、2024年のこと。
きっかけは主に3つあります。
住居購入を考え始めた最大の理由は、転勤による子どもへの心理的負担を減らしたいと思ったからです。長女の小学校入学を控え、今後も転勤生活が続けば、子どものストレスが大きくなるのではないかと感じていました。
夫の転勤スパンは3〜10年ほど。もし短い期間で転勤があると、長女は小学校6年間で2回ほど引っ越す可能性があります。入学直後や6年生の途中で引っ越すこともあり、そのたびに子どもには大きなストレスがかかります。
場合によっては、私と子どもだけがその場に残り、夫だけが先に転勤先へ行く選択肢もあります。ですが、万が一私に何かあったときに、助けてもらえる人が周りにいないのは大きなリスクです。
子どもたちには「ここが自分の地元」と思える場所を持たせたい。将来的にどこかに定住するのであれば、早めに動いたほうがいいと考えたのが、住宅購入を検討した第一の理由です。
家を購入する場合、戸建てかマンションか、注文住宅か建売住宅かなど、選択肢はさまざまです。
私たちは、いざというときに頼れる人が近くにいる安心感を重視し、私の実家近くのエリアで家探しを始めました。実家周辺は住宅地のため、自然と戸建てを中心に検討することに。
当時住んでいた場所から実家までは飛行機の距離で、頻繁に帰省するのは難しい状況。注文住宅よりも建売住宅の方が現実的だと考えました。
そこで、建売住宅を中心にいくつか物件を見せてもらうことに。
その中で、立地も間取りも理想的で、さらにそのエリアとしては割安に購入できる建売住宅を発見。
夫婦で相談した結果、今後の物価上昇も考えると、手頃な価格で購入できるのは今だけかもしれないと判断し、購入を決めました。
夫の会社では住居費の一部を負担してくれていたため、経済的にはとても助かっていました。短期的に見れば、賃貸に住み続けるほうが家計へのメリットは大きかったと思います。
しかし、会社の補助を受けている以上、もし夫に何かあった場合は住まいを失うリスクがあります。
また、定年まで勤めたとしても、退職後には社宅を出て新たな住まいを探さなければなりません。
いずれにしても、いつかは「自分たちの家をどうするか」を考える必要がありました。
夫はもともと「家賃を払い続けるくらいなら、いずれは自分の家を持ちたい」という考えを持っており、私自身もその考えに共感していました。
退職後に住宅を購入することも検討しましたが、ローン期間が短くなる分、毎月の負担が重くなります。かといって、現金で一括購入するのも、現実的ではありません…。
「家族にとって安心して暮らせる場所を作りたい」──そんな夫婦共通の思いもあり、私たちは持ち家を選ぶ決断をしました。
転勤族が家を購入する場合、一般的な注意点に加えて、転勤ならではの事情も考慮する必要があります。
- 希望エリアが遠方の場合は事前準備が重要
- 夫婦で話し合い、予算や希望条件の優先順位を決めてから見学に行くと効率的
- 収入や家賃補助の変化に備える
- 補助の打ち切りや収入変動で家計の負担が増える可能性があるため、余裕を持った予算設定と返済計画が大切
- 会社の補助制度やサポート内容を確認する
- 住宅購入前に、どこまで会社が支援してくれるか把握しておく
- 単身赴任の可能性がある場合は利便性もチェック
- 赴任先から自宅までの移動や生活のしやすさも考慮する
家を購入し、住み始めて約半年。
主に以下のようなメリット・課題を感じています。
これまでは、転勤のたびに仲良くなったお友だちとお別れするのが当たり前の生活でした。
辞令が出てから引っ越しまで、わずか1か月ほど。子どもたちは気持ちの整理をつける間もなく、新しい環境へと向かうことになります。
親としても、そのフォローには毎回とても気をつかいました…。
でも、定住地が決まったことで「次はいつ転校になるんだろう」という不確定さがなくなり、「この学校に6年間通うんだよ」「〇〇中学校に行くんだよ」と、子どもたちにも見通しを持って話せるように。
「もうお友だちとお別れしなくていいんだ」という安心感があるのか、子どもたちの表情もどこか穏やかです。
特に長女は小学生になってから、登校班やクラス、学童などを通して関わる人が一気に増えました。
少しずつ人間関係を築きながら毎日を過ごす姿を見て、「このタイミングで定住を決めて本当によかった」と心から感じています。
実家だけでなく、地元に引っ越してきたことで、これまで疎遠になっていた親戚や友人にも気軽に会えるように。
以前は、家事や育児は私がやらないと…!と常に気を張っていましたが、頼れる人が近くにいるだけで安心感が生まれ、心に余裕ができたと思います。
また、娘が小学生になったことや町内会への参加をきっかけに、人間関係が一気に広がりました。
このタイミングで定住したことで、自然に地域の人との関わりが広がったのは、私たち家族にとって大きなメリットだったと思います。
夫は単身赴任先で暮らし、私と子どもたちは自宅で生活するようになったため、2拠点分の生活費がかかるようになりました。
住宅ローンの支払いに加え、光熱費などの生活費もかかり、正直負担は大きいです…。
それでも、定住場所を決めたことで、私も落ち着いて仕事に取り組める環境が整いました。
今後は少しずつ収入を増やし、家計の負担をカバーしていきたいと思っています。
今回は、転勤族が住まいを選ぶ際のポイントと、我が家が持ち家を選んだ理由をご紹介しました。
転勤族が住まいを選ぶときは、賃貸と持ち家、それぞれの特徴を押さえることが大切です。
- 賃貸のメリット:引っ越しの自由があり、ライフスタイルに合わせやすい柔軟性
- 持ち家のメリット:住まいの安心感と資産性が得られる
大切なのは、「どちらが自分たちのライフプランに合っているか」を軸に考えること。
我が家の選択はあくまで一例ですが、ライフスタイルや家族の状況に合わせて判断する際の参考になれば嬉しいです!
-e1769411842466.jpg)

